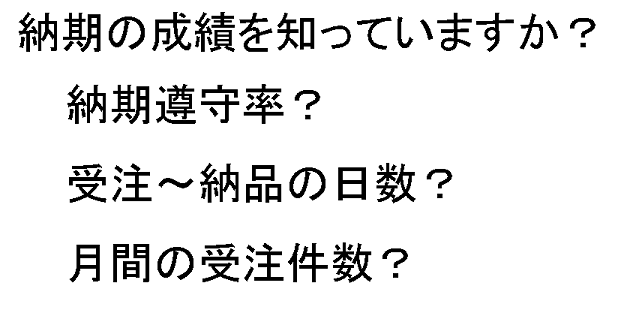| 納期半減の生産清流化 |
| トップページ | アルビスについて | 業務一流化 | 組織自律化 | 情報清流化 | 見積清流化 | 資料室 | リンク | お問合わせ |
| 慢性的な納期の悩みに効く生産清流化 |
|
1.納期遅れは生活習慣病である (1)納期の成績を知っているか 本稿は、慢性的な「納期病」に悩む製造企業に対して、改善の考え方と勘所を紹介するものである。「納期 病」とは、「納期を守れない」「納期が長い」といった症状が慢性的に続いている状態である。現代は、あらゆる製造業種で多品種・少量化・短納期化が進んでいる。短納期の重要性が叫ばれているにもかかわらず、それに対処できていない企業は多い。本稿はそうした企業における改善のヒントを提供する。 本稿は次の3つの章から構成されている。
1.納期改善の意義を知り目標を設定する 納期を改善する場合、その根本法則は単純である。つまり「仕事をやれば進む、やらなければ進まない」ということである。非常に当たり前の法則に支配されている。それにも関わらずなかなか改善が進まないのは、関わる人の心理が大きな障害になっているからである。納期を改善するには関係者が意義を知り目標を設定することが重要である。第1章はそれについて解説する。 第2章は、納期改善に取り組む場合に使う基本原則を紹介する。「納期改善」といってもいくつかの類型がある。また改善方策もいくつかに分類できる。それらを解説する。 第3章は、納期対策としてよく実施する事例を紹介する。目標の設定と実行組織に関するもの/現品管理と在庫に関するもの/加工と運搬に関するもの/日程計画と事務処理に関するもの/調達と外注に関するものを紹介する。 最初に振り返って欲しいのは、「納期の成績を知っているか?」ということである。「納期が問題だ」「改善したい」と思うなら、まず現状の成績を定量的に知ることが出発点となる。だが意外に把握できていない企業が多い。納期遵守率はどの位だろうか。受注〜納品の平均日数はどうだろうか。多品種少量と言っているが、月間の受注件数は何件だろうか。まずこれに答えられるようにすることが必要である。
|
| トップページ | アルビスについて | 業務一流化 | 組織自律化 | 情報清流化 | 見積清流化 | 資料室 | リンク | お問合わせ |