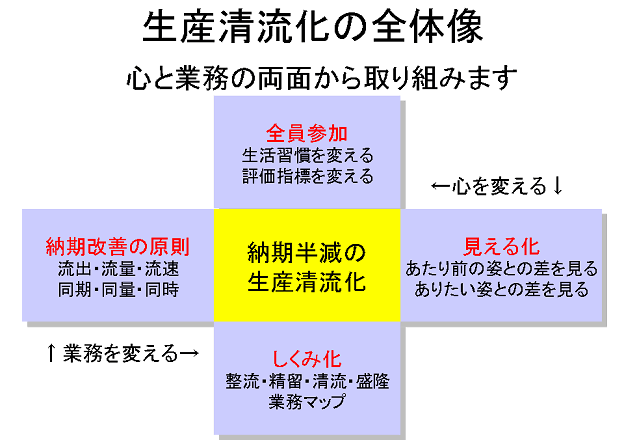| 納期半減の生産清流化 |
| トップページ | アルビスについて | 業務一流化 | 組織自律化 | 情報清流化 | 見積清流化 | 資料室 | リンク | お問合わせ |
| 慢性的な納期の悩みに効く生産清流化 |
|
2.生産清流化で心を変える (1)生産清流化の全体像 慢性的な「納期病」は生活習慣病である。日常業務の様々なやり方に原因が潜んでいる。業務のやり方とその背景にある心を変えなければ納期病は治らない。納期遅れの根源は「仕事を先送りする心」である。この心を捨てること、そして業務のやり方を変えることが治療の道である。 「生産清流化」は納期病の治療法である。心を変えること、業務を変えることの両面から取り組むプログラムである。心を変えるために「全員参加」と「見える化」を進める。業務を変えるには「改善方向と改善原則」を使いながら「しくみ化」を進める。 「全員参加」とは全社の全社員で取り組むことである。「仕事を先送りする心」を1人で変えるのは難しい。生活習慣を変える取り組みを全員でやることが重要である。その手段として評価指標を変える。納期に問題のある会社では納期に関する指標が整備されていないことが多い。野球でヒットが打てないと嘆くならば、まず打率を把握するのが普通である。納期が問題ならば「納期遅れが何パーセント」と数値で把握できることが必要である。 「見える化」も心を変えるための活動である。まず、「あたり前の姿」と現状の姿の差異を目で見えるようにする。例えばお客様に約束した納期は「あたり前の姿」である。約束した納期が関係者に常に見えるようにすること、残り日数を見えるようにすることが必要である。そして「ありたい姿」と現状との差異も見えるようにする。例えば受注から納品まで平均10日かかっているならば、ありたい姿は5日であろうか。そしてそれを達成するために何をやるべきかも見えるようにする。 「しくみ化」は業務を変える活動である。整流・精留・清流・盛隆と呼ぶ4段階のステップで重点対象を絞り込みながら、業務を変えていく。そのためには業務マップなどで業務の流れの構造を把握しながら進める。 「納期改善の原則」は納期を改善するために業務を変えていくときの原理原則である。納期改善には3つの類型がある。流出・流量・流速とはその3類型を表わすキーワードである。どの類型にあてはまるかによって対策方向が変わってくる。同期・同量・同時とは対策の考え方である。3種類の対策を組み合わせながら実際の対策を決めて実行していく。
|
| トップページ | アルビスについて | 業務一流化 | 組織自律化 | 情報清流化 | 見積清流化 | 資料室 | リンク | お問合わせ |