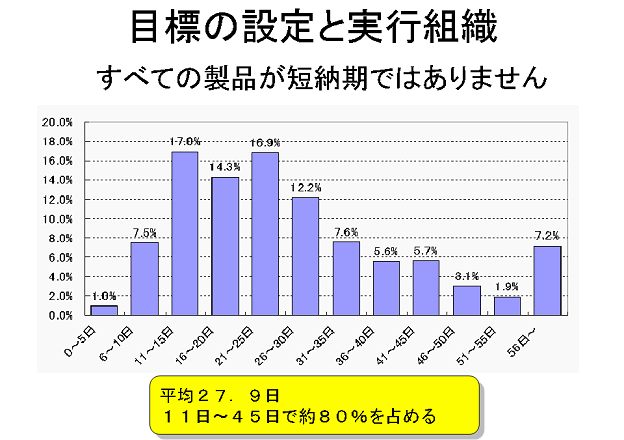| 納期半減の生産清流化 |
| トップページ | アルビスについて | 業務一流化 | 組織自律化 | 情報清流化 | 見積清流化 | 資料室 | リンク | お問合わせ |
| 慢性的な納期の悩みに効く生産清流化 |
|
4.納期対策の勘所と事例 (1)目標の設定と実行組織その1:要望納期の実態を知る 「生産清流化」は納期病の治療法である。本章では実行する場合の勘所と事例を紹介する。まず目標の設定についてである。 目標は納期遵守率や受注から納品までの日数で設定するのが一般的である。だが、納期病を抱えている企業では、その実態が把握されていないことが多い。「うちは短納期で...」という人は多いが、どの程度短納期なのだろうか。実態を数値で把握することが治療の出発点となる。 受注から納品までのリードタイムの実績値はもちろん、顧客の発注から要望する納期までの日数がどうなっているのかを数値で把握する。下のグラフは、ある企業において顧客の要望する日数の分布をグラフにしたものである。10日以下のものが8.5%ある。だがいちばん多いのは11日から15日のものである。21日から25日のものも多い。 2つの山があるのには訳がある。この企業では国内と海外の両方に販売している。国内の顧客は、11日から15日までが多い。一方、海外の顧客は月1回の発注・納品を前提としているため21日から25日が多いのだ。 一方、31日を超えるものも36.1%と多い。46日以上に限定しても17.2%ある。短納期を要望するものがある一方で、長いものも多いのである。こうした実態を把握した上で、受注から納品までの日数や納期遵守率の目標を設定するのが勘所である。
|
| トップページ | アルビスについて | 業務一流化 | 組織自律化 | 情報清流化 | 見積清流化 | 資料室 | リンク | お問合わせ |